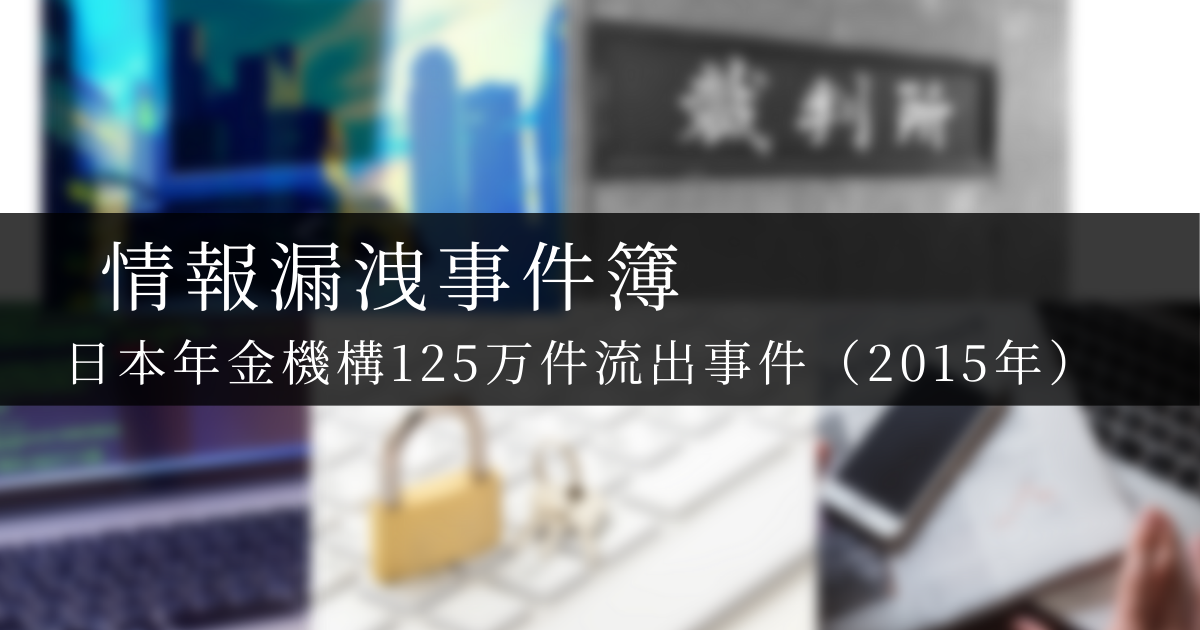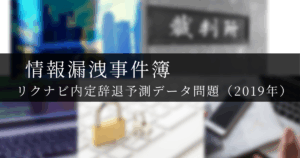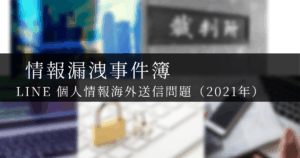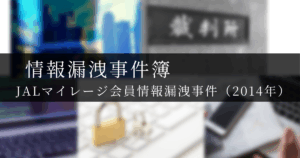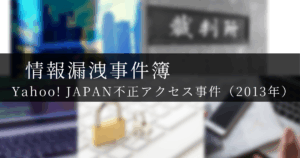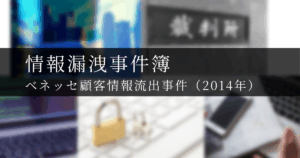目次
情報漏洩事件簿:日本年金機構125万件流出事件(2015年)
原因
- 職員が標的型メールを開封し、添付ファイルを実行したことが発端。
- ウイルス感染により内部システムに侵入を許し、大量の情報が抜き取られた。
- 職員へのセキュリティ教育不足と、多層防御が不十分だったことが指摘された。
つまり、一人の職員の操作ミスが大規模な情報漏洩に直結しました。
メール訓練やシステム的な防御を怠ると、どれほど大きな組織でも簡単に突破されるという事実を示した事件です。
企業対応
- 影響を受けた対象者への通知・謝罪
- 専用コールセンターの設置と問い合わせ対応
- 基礎年金番号の変更手続きの実施
- 全職員へのセキュリティ教育の強化
- メールフィルタリングや多層防御の導入
緊急的な対応とともに、組織全体のセキュリティ教育と体制強化に力を入れました。
特に番号の変更や全国規模での案内は大きなコストを伴い、社会的な影響の大きさが浮き彫りとなりました。
影響
- 約125万件の個人情報が流出し、国民生活に直接影響
- 「年金機構は安全ではない」という強い不信感を招いた
- 政府全体に情報セキュリティの見直しを迫るきっかけとなった
公共機関の漏洩は、単なる企業被害にとどまらず国民全体の不安感を引き起こします。
特に年金のような生活基盤に関わる情報が流出したことで、社会的インパクトは計り知れないものでした。
教訓(中小企業への示唆)
- 従業員一人の不注意が、組織全体の信用を失墜させる可能性がある。
- メール教育・標的型攻撃訓練・多層防御の導入は必須。
- 「人は必ずミスをする」という前提で体制を整えることが大切。
中小企業においても、標的型メールは十分起こり得ます。
だからこそ、教育と仕組みの両輪で備えることが、自社を守る最も現実的な方法です。
JAPHICマークで備える安心
JAPHICマークを取得した事業者には、情報漏えい保険(サイバーリスク保険)が自動付帯されます。
- 賠償責任支払限度額:500万円(免責0円)
- 情報漏えい対応費用支払限度額:200万円(免責0円)
(※売上5億円以下は自動付帯、5億円超は任意加入)
取引先からの「個人情報保護の証明」に応えるだけでなく、万が一のリスクにも備えられるのがJAPHICマークの大きなメリットです。
実際の導入を検討されている場合は、以下のページも参考にしてみてください。